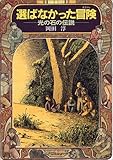昔の記録類を片付けていたら出てきた読書記録を見直していく。気軽な読みものもそれなりに読んでいたが、人間関係の本に絞って読書記録を取っていた。なんかすごいラインナップでお焚きあげ供養したくなったが、記録破棄ももったいないので、10年以上前の自分が思考的に迷走しまくっていた記念としてブログにあげておく。

対象喪失の乗りこえ方 ~別れ、失恋、挫折の悲しみを引きずらないために~
- 作者: 加藤諦三
- 出版社/メーカー: 大和書房
- 発売日: 2014/07/20
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る
対象喪失により誰もが傷つくが、その処理を間違え、自分の気持ちを抑圧したり現実から逃れようとしたりすると、それがツケとなっていつまでも囚われたままになってしまう。これを乗り越えることは最高の自分へ成長するきっかけとなるのに。まずはツケを払うことだ。傷と真正面から向き合い、悲しみ、断念することで前進することだ。
岡田尊司『パーソナリティ障害 いかに接し、どう克服するか』

パーソナリティ障害―いかに接し、どう克服するか (PHP新書)
- 作者: 岡田尊司
- 出版社/メーカー: PHP研究所
- 発売日: 2004/06/01
- メディア: 新書
- 購入: 58人 クリック: 1,188回
- この商品を含むブログ (72件) を見る
この著者の本は何冊か読んでいるが、どれもいい考えるきっかけを与えてくれる本だ。ちなみに以前は「人格障害」という言葉が使われていたが、いつからか「パーソナリティ障害」になったところに、大人の事情があるのかと勘ぐってしまう。
パーソナリティ障害は、偏った思考・認知・行動パターンのために生活に支障をきたした状態である。自分に強いこだわりを持ち、とても傷つきやすいが、根底には自己愛障害がある。幼い頃親に認められなかったために昇華しなかった承認欲求が肥大化していたり、対象恒常性が育たずその場その場の対応をその人のすべてだと誤認する「オールオアノン」の考え方をするのだ。
加藤諦三『嫌いなのに離れられない人 人間関係依存の心理』
この著者の本は何冊か読んだが、依存心、家族関係をテーマにしたものが多い。
依存心の強い人には不満と敵意と恐れという三つの傾向がある。要求が多く、裏には常に支配性があるが、それを満たされないがゆえに不満と怒りを抱き、なのに相手に嫌われるのが怖くて表現できないのだ。この敵意や、敵意を隠したときに生じる心の葛藤がコミュニケーションを破壊する。
斎藤学『インナーマザー あなたを責めつづける心の中の「お母さん」』

インナーマザー―あなたを責めつづけるこころの中の「お母さん」
- 作者: 斎藤学
- 出版社/メーカー: 新講社
- 発売日: 2004/01
- メディア: 単行本
- 購入: 4人 クリック: 16回
- この商品を含むブログ (15件) を見る
この著者は精神科医で、親と子の関係、それから生じうる病理の臨床症例経験が豊富だ。
親の望む自分を演じ、一定の役割を果たすことを期待された子供は、親から離れても自分の中にとりこまれたインナーマザーが「こうしなさい」と命令してくる。親の教義に従って必死に生きているけれど、自分自身の中身がなく、本当の自分はとても空虚だ。それを埋める相手を急いで見つけるけれど、悲劇的なのは、自分が育ってきたのと同じような機能不全家族をつくりあげてしまうこと。そこは慣れ親しんだ環境であり、居心地良いと感じてしまうからだ。
斎藤学講義集『心のうちの子供と出会う』
同じ著者の講義集。親の虐待がテーマだ。
現実の親は子供を二通りのやり方で虐待できる。一つは侵入すること、もう一つは条件付きの愛で愛すること。この両方とも、親は愛しているつもりで虐待しているというのが著者の見解だ。
子供が生き残るにはやはり二つ方法がある。一つは感情を鈍麻させること。こうすると子供は記憶を失うことになる。なんの意味もないからだ。もう一つは自分の中にいじめっ子を育てて自分をいじめること。いじめられる方の自分は本来の自分だから、いくらいじめてもかまわず、自分を痛めつけてダメさをとことん証明できる。そうすることで「それを批判する自己」という、わずかに力を持った存在が生き残ることができるからだ。
著者は言う。この二つの方法をやめさせる。そんなことをしなくてもあなたはそのままで生きられると、教えるのが自分の仕事だ。
田中俊之『男がつらいよ 絶望の時代の希望の男性学』
男らしくあれ、弱音を吐くな、働いて家族を養え、競争に勝て。そう生きることを義務付けられることは実はとても疲れる。
卒業→就職→結婚→定年という一本道をたどるのが難しい時代となっているのに、こうすることが価値がある、男らしい、とされている。男性は「競争」を要請され、このような「男らしい」半面多様性がない生き方を強いられるところに生きづらさの原因がある、と著者は書く。ライフプランを見直し、ワークライフバランスを考えるべきなのだ。
タル・ベン・シャハー『ハーバードの人生を変える授業』
すばらしい行動するためのワークを列記した書。感謝する、習慣化する、運動する、意義を見出す、といったようなことを、心がけだけではなく実際に書き出したりしてワーク化しているところが、いかにもアメリカらしい。